筆者紹介
ながしろばんり
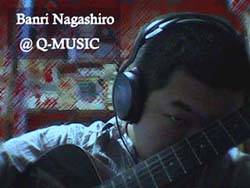
ここのところタイミングを逸してご無沙汰になっているながしろばんりさん。相変わらずあっち行ったりこっち行ったりの生活らしい。彼女が出来たという噂もとんと聞こえてこない。まあ、元気ならそれでいいのだけれど。本人曰く、ハウツー本のライターからエロ小説まで、基本的に頼まれれば何でも引き受けます。お仕事募集中。格安にて営業中。だそうですよ。 寄稿リスト| 寄稿リスト|
第1回
第2回コモンセンス
第3回グロテスク
第4回剥製〜短編小説論 I
第5回空間〜空間小説論〜
第6回破綻〜ライトノベル論
第7回萌え〜判官贔屓のリアリティ〜
第8回リアル〜『となり町戦争』を読む〜
第9回お役所〜文字・活字文化振興法案(前編)
第10回施策〜文字・活字文化振興法案(後編)
第11回興味〜よいこのブックガイド
第12回センス〜ダビデ王とマシンガン
第13回春は化け物
 |
| | 森羅万象
 書く人のための文芸事情 書く人のための文芸事情
|
| ながしろばんり 「書評のデュナミス」 第5回 空間〜空間小説論〜 |
まずは虱が登場する。「空間」というテーマだがどこから切ったものか、しかたなくミクロの穴を穿つ。自分の目で見えるものの最小のものといって思いついたのが虱である。虱あれ。すると虱があった。
我々の日常生活において一匹の虱、というのは考えにくい。虱なんぞいくらでもいるわけで、三十センチ四方に平均している虱をもって一単位ということにする。
「それっておかしいじゃない」どこかから声がする。「虱だって虱なりの虱権(なんて読むのかしら?)があるのよ。チャーチル先生が社会科の授業でそう仰っていたわ」
なるほど、たしかに虱にゃあ単数系[louse]と複数形[lice]がある。[a lice]がみょうてけれんということか。
「あ、でも」声の少女は幾分ばつの悪い声をだす。「いいかも、わたしと同じ名前だし」
[Alice]
というわけで「不思議の国のアリス」である。意外だったろうか。意外かもしれない。ロマン文庫から『鏡の国のアリス』なんて官能小説も出ていたが、今回取り上げるのはもちろん本編アリスである。『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』ついでに初校版である『地下の国のアリス』も挙げておこうか。
アリス研究の本は汗牛充棟、世界各地で研究者が喧々囂々侃々諤々、アリスのレトリック、暗喩性、禅やタオイズムとの関連性、処女性、エロスとの関連、ひいては作者であるチャールズ・ラトウィジ・ドジソンの幼女趣味から書簡マニアぶりまで出尽くした感がある。筆者もこの神経質で知りたがりでペダンチック(これをアリスの三大条件と勝手に確定)な少女に惹かれてつらつらと読み漁った身なのであるが、今回話題にしたいのは、アリスが日本に渡ってきたときの評価、という点である。
日本における、いわゆる「純文学」はおおむね「私小説」というカテゴリーとの関連を逃れられないことになっている。それは、十九世紀フランスの自然科学が明治時代の日本において大きな誤解を持って迎えられたかたち、すなわち、フランスのそれにおける<理想化を行わず、醜悪・瑣末なものを忌まず、現実をただあるがままに写しとることを本旨とする(広辞苑)>という原意から、日本文学での<人間の業やドロドロした物をありのままにさらけだすものが小説>に変貌していったところを根として、実は今現在の日本でも、根本的な価値判断は変わっていないのである。
純文学――結局は文学のコアってなんだ、という問題が拠点であるときに、日本の文学はこの自然主義に根ざしているところが大きいといえる。私小説についてはまた別項にて述べることにしたいが、とまれかくまれ、人間の内面や業の追求・描写というものが、日本の文学においての判断基準であり、筆者もその流れには賛同するものである。内面という不可視なものを可視にするものとして、藝術としても強い説得力を持っていると考える。史上最年少芥川賞の綿谷りさ『蹴りたい背中』は読まれたろうか。ノブ・モリオ『介護入門』読まれたろうか。彼らの作品は、いわゆるblog的日記の延長線上の問題として、今この時間の、この場所の、この人々、の正鵠を得ているから、純文学として評価されるのである。
日本の文学的カテゴライズからすると、『不思議の国のアリス』は「ナンセンス文学」となっている。
確かにアリスにおける色々の遣り取りは「ナンセンス」つまりは頓珍漢なものも多分にある。「カラスと書きもの机、どこが似てる?」というなぞなぞは「わし、しゃっぽぬいだよ」なんて、答えのない問答であったり、腹が立つたびに首を刎ねろと命令する女王やみんなが好き好きに走り始めて好きなところでやめるために全員が一等賞の「コーカス・レース」など、確かに、作品に充溢するニュアンスは"nonsence"である。だがしかし、それはナンセンスだろうか。つまり、日本人が辞書を引いて得られるところの「ナンセンス」だろうか。広辞苑には<無意味なこと。くだらないこと。馬鹿げたこと>とある。筆者にはむしろ、日本の私小説的価値観に当てはまらない存在たる「アリス」を「ナンセンス=ばかばかしい!」というカテコライズに隠蔽してしまったように思えるのだ。確かに、アリスには内面の発露、人間の暗黒面、作者による意図的な内面追及は無いといっていい。
ナンセンス文学に属するものを他に挙げろといわれればマザーグースを皮切りにジョイス『フィネガンズ・ウェイク』、日本なら夢野久作『ドクラマグラ』。文学作品がお好みではないという場合は、さくらももこ『コジコジ』などいかがだろうか。『コジコジ』も『メルヘンの国』という枠があって、その中で展開するものは独自の法則性に統一された「世界」である。作者の創造しあげた世界の中で、登場人物が遊んだり、騒動を起こしたりというイベントがある、という作りである。一方、日本の私小説的価値観は、「ナンセンス」というカテゴライズ自体に「内面の無いもの=小説として不充分=まともではない」という観念を持って接してきたと考えていい。
そう、小説が芸術の一ジャンルとして、不可視の存在を可視にするものであるにもかかわらず、一人の作者が<空間を作り上げる>文学は、日本において本筋ではありえなかったのである。建築家が壮麗な寺院を作るごと、数学者が一点の破綻も無い数式を完成させるがごと、文章から発する閃光的なもの、完成されたトリック、精密な構築についてないがしろにされてきた面は少なくない。
そこで、イマジネーションが生み出す「空間性」の文学を、さしあたって「空間文学」と呼ぶことにする。日本の多くの小説家が内面追求に血道を上げていたのに対して、空間ディテール、そして秩序の作成に血道をあげる芸術家がいるのである。キャロル、本名チャールズ・ラトウィジ・ドジソンがリデル家の三姉妹、とりわけ次女のアリスのために作り上げた「空間」の小説である。こう考えてみると色々当てはまる。言語の多義性からいわゆるジョイス語で小説を構築した『フィネガンズ・ウェイク』、息子クリストファーと仲間たちが百エーカーの森に棲むミルン『クマのプーさん』、神様が天地を作り終末へ向かう『聖書』、曼陀羅による宇宙原理のコアを示した『般若経』、ムハンマドの受けた啓示、つまりイスラム世界の取扱説明書であるところの『クルアーン』、以上、異論もあるだろうが(※)<空間創造>というカテゴライズにおいて共通する点が一つだけある。すなわち、それら「原典」を元として数多の教派が立っているという点である。結局宗教の経典というのは、それぞれの地域における世界の取扱説明書みたいなもので、取り説をもとに各派がそれぞれの解釈を展開するのだといえる。日本の仏教が真言宗、日蓮宗、曹洞宗……なんて分かれるのと同様、アリスの世界を禅の思想になぞらえて読み解いたものや、クマのプーさんを老荘思想によって読み解いたものなどの自己啓発本が出ているけれども、あれも突き詰めてしまえば『アリス』という空間の原典から独自の解釈を提示している時点で、一つの別の宗派なのである。仮に出発点がタオとの類似性だったとしても、クマのプーさんの空間への解釈としなければ、執筆動機がわからなくなってくる、というのが根拠である。
話が横にそれてしまったが、私小説が内面を描き出すのと同様に、非−世界である空間を描き出すのにもそれなりの執筆動機が必要となってくる。ルイスキャロルの場合は、好きな女の子を愉しませるためである以上に、同名のアリスちゃんを不思議な空間で困らせ、迷わせるという強力な意志があったように思うのだ。空間性の文学、それは例えば近年の『ハリーポッター』シリーズのホグワーツのディテールでもあるし、日本の中世から江戸にかけて流行る地獄絵図に関しても同様のことが云える。作者のイマジネーションの強さは先天的なものなのかもしれないが、一人の人間のイマジネーションが超・世界を作り上げることの戦慄を、もっと評価してもいいのではないかと思うのである。
※ 異論あるだろう。うちの教典は神の言葉であり、人間が作ったものではない、などの指摘である。だがしかし、それを人間を通して、人間が受け取れるようにした時点で一つの著作物であるという把握で了解いただけないだろうか。むしろ、筆者は信仰とは別次元の問題として「空間性」を問いたかったものと理解していただきたい。為念。
参考文献
・ステファニー・ラヴェット・ストッフル/高橋宏訳/笠井勝子監修 『「不思議の国のアリス」の誕生』(創元社、1998年)
・高橋康也編『アリスの絵本』(牧神社出版、1973)
・ちなみに日本の私小説的な価値観の形成については越人流文章講座・第八講におおまかにまとめてある。参照されたし。
<http://www5a.biglobe.ne.jp/~banric/600/class.htm#8>
アリス本文についてはマーティン・ガードナー注、高山宏訳『新注 不思議の国のアリス』(東京図書、1994)を参照した。上記のカラスのなぞなぞについて、のちに発表されたキャロル自身の解答など、注釈が詳細を究めている。
しかし、ルイスキャロルの偏執的な言葉遊びぶりをもっとも伝えているのはちくま文庫版(柳瀬尚紀訳)ではないかとおもう。並読されたし。05/2/26/NAGASHIRO
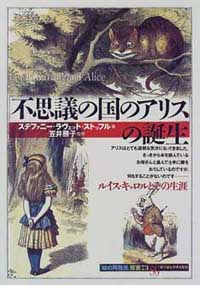
写真▲『「不思議の国のアリス」の誕生』(高橋宏訳/笠井勝子監修・創元社)

写真▲『鏡の国のアリス』(柳瀬尚紀訳・ちくま文庫版) |
|
| | |   
当Webサイトは FLASH PLAYER の最新バージョンを必要とします。 |
 |