筆者紹介
ながしろばんり
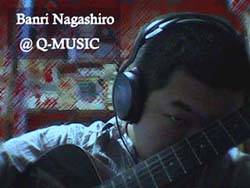
芸人。日本大学芸術学部文芸学科卒。著述から編集、イラストレーション、作詞作曲弾語りまで幅広くこなす大いなる器用貧乏として活動中。現在は編集者を経てフリー。亜空間創作ギルド万里園主宰、オンライン文芸集団・文藝越人六〇〇主宰。いくら仕事をしてもパッとしない仕事ぶりは「無冠の帝王」として語り継がれている。ハウツー本のライターからエロ小説まで、基本的に頼まれれば引き受けます。お仕事募集中。格安にて営業中。 寄稿リスト| 寄稿リスト|
第1回
第2回コモンセンス
第3回グロテスク
第4回剥製〜短編小説論 I
第5回空間〜空間小説論〜
第6回破綻〜ライトノベル論
第7回萌え〜判官贔屓のリアリティ〜
第8回リアル〜『となり町戦争』を読む〜
第9回お役所〜文字・活字文化振興法案(前編)
第10回施策〜文字・活字文化振興法案(後編)
第11回興味〜よいこのブックガイド
第12回センス〜ダビデ王とマシンガン
第13回春は化け物
 |
| | 森羅万象
 書く人のための文芸事情 書く人のための文芸事情
|
| ながしろばんり 「書評のデュナミス」 第2回 コモンセンス |
さあ、第二回目から中ボスの登場である。表現者としてこれに亜党うものは下、打ち勝つものは中であり、背後に回るものは上であるという。なにやら箴言くさいノリで恐縮だが、前回宣告したしりとり法により今回、表現におけるコモンセンスの話である。
大体この辺り、語義から引っ張ってくるのが順当ではあるが、単に広辞苑や大辞林を引くのでは面白くない。大体用語集マニアというのはどこの団体や業界にも一人や二人いるもので、本棚を漁るとありましたありました、中村雄二郎、その名もずばり『述語集』から。
<コモン・センス>はふつう常識と訳され、ときに単なる常識、つまり、ありきたりな考え方として、ときに健全な常識、つまりはバランスのとれた大人の考え方として、うけとられている。すなわち、常識は学問的な知識、学知(エピステーメー)と比較されて、前の場合はより表面的な知、後の場合はより経験に裏付けられ、物事の多くの側面を顧慮した知とされたわけである。
(中略)
コモン・センスとは、公共の福利と共通の利益とについてのセンス、共同体や社会への愛、自然な感情、人間らしい心、親切、人間共通の権利についての正当な感覚に由来するような種類の丁寧な態度、および同胞の中での自然の美質のことである。(筆者による傍線、原文は傍点)
困るんだわなぁ、こういうのが。
先に結論だけ書いてしまえば、二つの要素を混紡しているから反発を招くのですな。一方は社会生活を円滑にやるための「知恵」であり、もう一方はある思想体系に裏打ちされた「お約束」である。話の都合上、前者「知恵」、後者を「慣習」とでも呼んでみようか。つまりこの「慣習」についていけない場合、かならず反発が起きるわけである。コモンセンスの出所は大英帝国で、確実にキリスト教的な倫理観が前提となって語られていることも忘れてはなるまい。
一方、じゃあ日本における常識とはなんなんだ、といえば日本常識力検定協会という団体があるので、そこでの見解を引いてみよう。
常識はいつの時代でも、社会を生きる人にとって基本的な存在条件ですが、社会は常に進展、変革を求められ変化しつづけています。(中略)お互いが相手のことを考えて会話や行動をするとき、どんなに時代が変化しても、人間としては変わらないものがあります。その共通認識である知識や表現を再度「常識」として捉えなおし、それらを統合した力(人間力)が「常識力」なのです。(※2)
なるほど、こっちのほうが時勢に即している。常識は常に変化して行くものだが、根底には変化しないものがあって、その固い部分を再認識しよう、ということらしい。日本における「常識」も、やはり「慣習」としての常識となる。もっといえば、「慣習」に根づいた「知恵」が総体として「常識」なのであって、われわれが「常識」という言葉に違和感や嫌悪感を覚えるときには、常識がおのれのいるべき範囲から越境している、ということになるのだ。
だがしかし、その根底たるものが粉みじんになってしまったのが現代の日本ではないのか。慣習としてあったものを新たに「有用なもの」として提示しない限りり、需要に対する供給として通用しないだろう。古きよきものを再評価する場合、それは全て有用かファッションかで判断されるのだが、この辺に、やはり「常識」というものを振りかざす連中の限界が見える。「こうなっています」では通用しないゆえに常識が損なわれているのであって、そこに「慣習として」しがみついているうちに発展はない。「慣習」が確実に「知恵」を阻害しているのである。
このまま『術語集』を負いかけて行くのも面白いが本筋から外れるので乗り捨てる。小説という現場においての「慣習」と「知恵」である。ようやく本題である。本題に入ったことで祝日にしていいぐらいの目出度さであるがさて今回、小説における「風景」の問題だったのである。作家の中沢けい御大はこれを「共感の回路」と呼んでおられる。この共感の回路とは今まで申し述べたような「常識」とは一線を画す。いわゆる語義通りの、「共通」の「感覚」である。
例えば、曇り空の港。防波堤にトレンチコートの男、女――はなんでもいいや。売笑婦でもヤクザの愛人でも、なんだか危うい感じの女性。ウミネコがクウクウ鳴いて、遠くのほうでは蒸気船が、ボーっ。
年配の方であればあるほど、あー、なんて思われるのではないか。別れのシーンである。大体、男と女ったら海なのである。『金色夜叉』で貫一がお宮を蹴飛ばしてから先(笑)、あやうい関係の男女は海へ向かう。渚にゃシンドバッドも出る。なんでだろうね。なんでだったら、それが日本人の「共感の回路」だからなのである。だから、海で遊ぶ母と子、なんて書かれても、そこに片親だとか、悲恋だとかをいうニュアンスがついてまわる。これは「慣習」でも「知恵」でもないわな。日本人が感覚として掴んでいる「共感の回路」なのである。ロジックでないからこそ、創作というジャンルでこの回路が生きてくる。つまりは、小説書きとして、この「共感の回路」をいくつ探り当てているか、というのが一つの重要なファクターであると考えるのだ。コモン・センスをうまく捕まえて、小説の枠組みとして利用できるようであれば、読者としても、作品に対しての安心感が違うのである。
具体例をあげてみようか。小説の名手なら誰をあげてもいいのだが、純文学でないほうがどのジャンルにも当てはまることがわかるので、筒井康隆を引いておこう。新潮文庫版『薬材飯店』より。
ある日おれは散発にいった帰途、下山手通りから国鉄三宮線に出る路地を抜けようとした。「薬菜飯店」を見つけたのは、近道をしようとして南北に通じる路地へ入った時である。間口わずか一間、数階建てのビルの裏に密着して、その小さな中国料理店はひっそりとうずくまっていた。戸の片側のわずかな壁を利用してショウ・ウィンドウがあり、その中には手書きのメニューが一枚貼られているだけである。
薬菜各種献立
鼻突抜爆冬蛤(肥厚性鼻炎治癒)
味酒珍嘲浅蜊(肺臓清掃) [略]
「薬菜飯店」という作品自体は筒井康隆一流のグロありエロあり美味有りの痛快SF短編であるので各自読んでいただくとして、SFといえど、舞台である薬菜飯店という空間をここまで端的に作り上げているところが、実はプロの仕事なのだといえる。これを、<路地裏のうらぶれた中国料理屋>なんて書いてみて御覧なさいアータ、始めっからそんな立地条件の悪いところに立てたのか、始めは立地条件がよかったのだが開発により裏路地になってしまったのか、それとも、当初は人気の店だったのだけれども、主人が死んで長男が後を継いでから酷い店になってしまったのか。要は絵画におけるデッサンと同じで、一つのリンゴを描写するにしても、そのリンゴそのものだけではなく、リンゴの存在する場所の空気まで描けないと実感として伝わらない、のである。
後の阿鼻叫喚なドタバタを、この数行の描写が支えている。詳しくは言わないから、読者各位、一読をお勧めする。
というわけで、今回は「共感の回路」の話でありました。ではまた。
今回の課題図書
・井上ひさし『黙阿弥オペラ』(新潮文庫、1998)
・豊田正子著 山住正己編『新編 綴方教室』(岩波文庫、1995)
今回のテキスト
・中村雄二郎『術語集―気になることば―』(岩波新書、1984)
・日本常識力検定協会『あなたの常識を10倍にする本』(実業之日本社、2004)
・筒井康隆『薬菜飯店』(新潮社、1982)04/11/27/NAGASHIRO
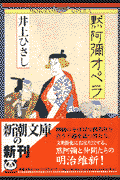 
写真▲『黙阿弥オペラ』『薬菜飯店』
|
|
| |   
当Webサイトは FLASH PLAYER の最新バージョンを必要とします。 |
 |