筆者紹介
ながしろばんり
小説・編集・評論・弾語・Webデザイン・イラストレーション
 筆者近況◎ 筆者近況◎
1980年、東京都三鷹市生まれ。日本大学藝術学部文藝学科を卒業後、文藝出版社勤務を経て現在はフリー。師匠は文芸評論家の多岐祐介。
中沢けい公式サイト「豆畑の友」管理人他のウェブサイト管理をはじめとして、2005年1月にはイラストと本文を手がけた『貴方の常識力を10倍にする本』(実業之日本社)を刊行。その他、文芸雑誌「文藝矮星」、ヘタレエンタテイメント雑誌「五蘊冗句」(現在は休刊)編集長。
また、評論ではポントルモ文学書斎にて『書評のデュナミス』連載中、筆をギターに持ち替えて弾語アルバム二本、小説では「火喰鳥」で徳間書店「新世紀小説バトル」最終選考。亜空間創作ギルド万里園主宰、文藝越人六〇〇主宰、と偉大なる器用貧乏振りを遺憾なく発揮。文藝不一会幹事。オンライン文学賞「矮星賞」選考委員。
なお、今年はエンターティメント批評のフリーペーパー『ルクツゥン』デスク。 寄稿リスト| 寄稿リスト|
第1回
第2回コモンセンス
第3回グロテスク
第4回剥製〜短編小説論 I
第5回空間〜空間小説論〜
第6回破綻〜ライトノベル論
第7回萌え〜判官贔屓のリアリティ〜
第8回リアル〜『となり町戦争』を読む〜
第9回お役所〜文字・活字文化振興法案(前編)
第10回施策〜文字・活字文化振興法案(後編)
第11回興味〜よいこのブックガイド
第12回センス〜ダビデ王とマシンガン
第13回春は化け物
 |
| | 森羅万象
 書く人のための文芸事情 書く人のための文芸事情
|
| 「書評のデュナミス」 第12回 センス〜ダビデ王とマシンガン |
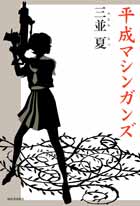
三並夏『平成マシンガンズ』(河出書房新社)
(自称詩人禁制)
前回、好評だったようでたくさんの反応をいただきました。そうなのよ。面白いのに人の目に触れなくなってしまっている、というのは伝える側の言い訳であり、下手糞なところなんである。そもそも芸術、芸なんぞ実質的には何の役にも立たんのよだし。ただ人間が生れて学校へいって働いて死ぬ、この途上にある隙間でしかない。その隙間ごとき、文学だの芸術だのが崇高なものだって気持ちが創る側にちょっとでもあればそれはそれでろくでもねぇ。
だが、その間隙がなければ人間なぞちょっとしたショックでポッキンといっちゃう。力道山だってナイフで刺したら死んぢゃうんだぜ。あんまり関係ないか。
くだらねえことを大真面目にやるから面白い。読者だってくだらねえと思いながら面白がりゃ、いいんでないかな。作者にとっても読者にとっても一番六づかしい(漱石風)ことでありますが。
本コラムも十二回目、とうとう一年続いてしまったので大ネタやります。河出書房新社「文藝賞」史上最年少受賞者三並夏「平成マシンガンズ」だって。世間一般的には立派なネタであるようです。美人女子中学生が低迷する文学界に新風を吹き込む! 込まない込まない。アレから綿谷理沙がなんかしたか。金原ひとみがなんかしたか。そんなもの込んでるの見たこと無いし、おそらく込むことも出来ないだろう。何でかといったら、コレはひとつの「通過地点」だからだ。マスコミのおなかが一時膨れるだけですよ。ひっかかっちゃあいけない。
でも、面白いかっちゃあ、面白いですよ。何が面白いって、選考委員選評で、高橋源一郎だか田中康夫だかが「話題性のために選んだんぢゃない、偶さか十四才だっただけだ」なんて云ってるあたりが。河出「文藝」編集部も話題作りのための選考はしていないといっている(選考委員コメントより)。ああ、まともな編集者だった、なんて、内輪で安心してどうする。
話の筋は単純。学校でいじめられている朋子という主人公、親は実業家だかなんだかで娘には目もくれない。そのわりには二号さんが家の中ででかい顔をしている。元のおっかさんは家を飛び出している。学校の教員はエゴイストの馬鹿ばっかりだ。そんな中でも朋子は元の家庭に戻そうと奮闘する、が、うまくもいかずおっかさんの家に飛び込むが、二号の弟(無職)は離婚届をもっておっかさんに詰め寄ってるし、おっかさんは「離婚する気は無い」って突っぱねるわ、もうどうしようもなくって、朋子は全てを受け入れて、開き直ってやっていく、と。そういう話。単純明快。明快すぎて、何も、見えない。
だがしかし、結論から云ってしまえば、この作品、「文藝賞」とってしかるべき作品だったと思う。それだけ、現在の平成日本に必要な要素はあったように思う。文章もグダグダ、中学生の語彙で、登場人物もいかにも漫画チックでありきたりのことしか言わないし、状況に対して一人相撲のところもある。だがしかし、だがしかしだよミナサマ! この小説の凄さというのは、そういった国語力、気迫、気持ちや視野の狭さも含めて、ほぼ完璧な形で噛みあっている、ということなのだ。大体モノかき始めて(変な意味じゃないぞ)しばらくたつと自分自身を保っているバランスに無理が出てくる。例えば見栄っ張りなおかげで自分の天分に合わないことをしたり、文藝オタクになって理論ほど体が動かなかったり、その逆にエネルギーは有り余っていても舌や筆や言葉が追いつかなかったりする。筆者なんぞある意味開き直ってグダグダやっていますが、これだって自分の知識だの実践だの気力だの自信だのに下駄ァ履かせて演っているわけで。下駄ァ履いているという意識がある時点ですでに駄目なんですな。誰だって朝七時に家を出て夜の十一時時だか十二時だかには帰りたくはないでしょう。ただ、生きるために自分に下駄履かすわけで。それと同じことなんじゃあないかね。
思い起こしたのは、小説としてどうか、ということよりもむしろ文藝の根源についてであります。
言葉の効用の第一は、意思の伝達である。だが、犬の遠吠えから人間の言語になった時に、情報の伝達以上のものを求めようとする。これを「文藝」とすると、祖である「詩」の力というのは、この「言」に何がしかの力を持たせるということなわけで。
最高最強の「詩」というのは言葉=存在であるというイマジネーションであります。水木しげるのベリアルなんぞ「ホットケーキ!」ったらホットケーキが手の上に出てくるし、それが漫画だったとしても、どこだかのバイブルじゃはるばる二千年前近い昔から「光あれ!」なんてことを演ってても「漫画じゃないんだから」なんて突っ込みははいらない。目に見えないものだったらホットケーキよりも出しやすい。言葉によって人が喜んだり、悲しんだり、そういった類のことはありますな。
高橋睦郎の『詩人王攷序説』なんかを頑張って読むてぇと、詩人王ことホメロスの「オデュッセイア」のことが書いてある。先ほどににも申し述べたように、いわゆる神が天地創造をする。神というのは人間の感覚で捉えられないから神なのであって、偶像にして目に見えちゃうようにするのは冒涜だ、というのがイスラム教他一神教の言い分でありますが、その神の言を預かって人間どもに告知する、というのは万国共通だったようで、イスラムにおける預言者、日本の卑弥呼、中国の皇帝(※)、ダビデ王、このあたり、神から言葉を預かる者が王(road)=詩人であるわけだ。オデュッセイアにおいては、王を慰める役目だった楽師が寵愛を受けて、結果として王の武力をも手に入れることで「詩人王」として完成したということで。まぁ、ゆくゆくはこの「詩人王」も霊性の衰えから別に「神官」なる職業をおくことになるわけだけれども、こうなると日本製RPGの世界でありんすな。
さて、と。「平成マシンガンズ」に戻るけれども、本作品、霊性の復活なんぢゃないかなぁという話なのです。霊性の衰えってのは、つまりは自分自身のどこかに無理が出始めているということ。相応の生活を送れない(出来ない)、年をとってからだが衰える、欲がたたって危険を冒す、見栄を張って無理をする、などなど。
日本人の勤勉さが外国に受けいれられない。週四十時間労働だとか云われたって守っている会社なんざナイ。日本人にゃ日本人の労働時間がある。人間、元気なうちに働いて疲れたら休むのが一番いいんだけれども、そうもいかない。そもそも、そういう生活リズムを奪ってしまったのは戦後の高度成長だったかもしれない。前にも同じようなことを書いた気がするけど、良かろうが悪かろうが、無理をすりゃどこかに皺寄せがくるモンで、結局実利で成果を上げる一方で、精神的なもので充足を得られる場所を潰してしまったように思う。文化的な成熟がないゆえに、金稼いで財を残すことにしか幸福感を見出せなくなっている、ということだ。言い換えれば、目標を設定しないことには行動できない体になっている、ということだ。そういう意味では、まだ日本は戦争の爪あとを遺しているともいえる。文化的な伝承や構築、古くから生き残っているものの生き残った「理由」を金が蹂躙しようとする。神が死んだ後は金が神になって今度は自分自身が神になっちまった。
「平成マシンガンズ」は、心技体見事にバランスの取れた新世代の作家が、いわゆる「詩人」としての言葉を見せてくれたような気がする。年齢ゆえの文章の勢いに見えるかもしれない。しかし、それはあたかも、戦争が終わって、無理をして立ち直った日本が体を病んで、ようやく健康を取り戻した大あくびのようにも見える。戦争の加害者も被害者も経験して、ようやく五体満足な日本人が生まれてきたのではないか、という期待である。本作、筆者も選考委員と同様に今後の活躍に期待したいと思う。
是非、興味を持たれたら読んでみるといいと思う。でも、「言葉」の気迫以外、なぁんにもないぜ、この小説。それが面白いのだけれども。
※中国の皇帝については違和感を感じる向きがあるかもしれないが、天帝から委任されて、という形での即位なのである。その証拠として、中国においては「列伝」として皇帝の政治から悪事まで厳密にかかれている。ここにおいて皇帝の悪事を隠匿しない、というのがミソであります。
■参考文献■
三並夏「平成マシンガンズ」(河出書房新社「文藝」2005年冬号)
高橋睦郎「詩人王攷序説」(出典不明)
水木しげる『ゲゲゲの鬼太郎』(5、講談社、昭和60年)
05/11/27/NAGASHIRO |
|
| | |   
当Webサイトは FLASH PLAYER の最新バージョンを必要とします。 |
 |