筆者紹介
ながしろばんり
小説・編集・評論・弾語・Webデザイン・イラストレーション
 筆者近況◎ 筆者近況◎
1980年、東京都三鷹市生まれ。日本大学藝術学部文藝学科を卒業後、文藝出版社勤務を経て現在はフリー。師匠は文芸評論家の多岐祐介。
中沢けい公式サイト「豆畑の友」管理人他のウェブサイト管理をはじめとして、2005年1月にはイラストと本文を手がけた『貴方の常識力を10倍にする本』(実業之日本社)を刊行。その他、文芸雑誌「文藝矮星」、ヘタレエンタテイメント雑誌「五蘊冗句」(現在は休刊)編集長。
また、評論ではポントルモ文学書斎にて『書評のデュナミス』連載中、筆をギターに持ち替えて弾語アルバム二本、小説では「火喰鳥」で徳間書店「新世紀小説バトル」最終選考。亜空間創作ギルド万里園主宰、文藝越人六〇〇主宰、と偉大なる器用貧乏振りを遺憾なく発揮。文藝不一会幹事。オンライン文学賞「矮星賞」選考委員。
なお、今年はエンターティメント批評のフリーペーパー『ルクツゥン』デスク。 寄稿リスト| 寄稿リスト|
第1回
第2回コモンセンス
第3回グロテスク
第4回剥製〜短編小説論 I
第5回空間〜空間小説論〜
第6回破綻〜ライトノベル論
第7回萌え〜判官贔屓のリアリティ〜
第8回リアル〜『となり町戦争』を読む〜
第9回お役所〜文字・活字文化振興法案(前編)
第10回施策〜文字・活字文化振興法案(後編)
第11回興味〜よいこのブックガイド
第12回センス〜ダビデ王とマシンガン
第13回春は化け物
 |
| | 森羅万象
 書く人のための文芸事情 書く人のための文芸事情
|
| 「書評のデュナミス」 第8回 リアル〜『となり町戦争』を読む〜 |
デュナミスもいいけどたまには新しい作品をやったらどうかね、と誰だかに言われたので新しい作品をやることにする。誰だか、というのは誰だかであって、決して誰か特定のどなたかではないのンである。ヤヤコシイナオッチャン!
ところがちょうど河出の文藝賞が第百回なのでこいつはいいや、と思ってみてみると、やんぬるかな該当者なしときたもんで、どうもあれですな、本稿、やることは決まっているのだけれどもなんかサンプルがないと面白くないし、読むほうだってつまらないだんべえ、ということで。
というわけで今回は『となり町戦争』(三崎亜記、集英社)でござい。去年のすばる新人賞作品。なにがすごいって、井上ひさし、五木寛之、高橋源一郎、業界に名だたる偏屈が絶賛しており、へぇ。とまぁ、権威に阿党うのはよくないことですか。いいとも悪いとも思いませんが場合によりけりだと思います。OK安心した。酔ってんねやなオッチャン!
さて、真面目な話はさておき、『となり町戦争』。おおむね純文学と我々が普段呼んでいるものについては、大きく二つあると考えていいと思う。人間の普遍的な性(さが、ですよ。セックスとしか読めない人が多くてばんり困っちゃう)を描いている部分、そして、その時代ごと、その時代の風を取り扱っているもの。最近の芥川賞作品はこの『時代の風』というやつが大好きで、何故かといえば、それえけ作者自身の視点や創作に掛ける意気込みが問われるからである。ネット小説書きを初めとしたいわゆる「志望者」においては、普遍的なテーマのほうがとっつきやすいし、周りの人間が見てもあまりこっぴどくは突っ込まないゆえに書いてしまいがちなのであるが、ひいてはちょろっとその「普遍性」の匂いさえさせておけば、一般の読者なんか騙せてしまうだろう、という気持ちゆえであって、その普遍性に対峙できるまで執心しないがために、普遍性を書き出すことに成功したためしを筆者は見ないのである。(分別のついた人間がどこまで真面目に取り組むか、というところがネット小説そのものに問われている気がするな、昨今)
で、本作は「戦争」を取り扱ってる。舞阪という町に通勤の都合で二年前から住んでいる北原という男が主人公。ある日町報である「広報まいさか」で【となり町との戦争のお知らせ】なんて記事が載る。開戦九月一日、終戦三月三十一日。かといって、通勤のために車でとなり町を通るのだけれども取り立てて変わったこともない。戦争なんてないんじゃないか、と思っていると次の市報で<死亡23人/(うち戦死者12人)>なんて記事が載る。実感のないところで、戦争は確かに起こっている。と、この小説はとなり町との戦争を中心に描いているのだ。今の日本人の戦争への意識をレリーフした優れた作品である。
といっても、いいんだが。
おかしいのよ、この作品。「となり町との戦争」ったって隣接する町はいくらでもあるし、もし小説どおりに「戦争」が慣例化しているならば、もっとマスコミが騒いでいいはずだし、そもそも、北原自信が感じている違和感に対しての説明がないことになってしまう。北原は市役所からの依頼によって「となり町への偵察任務」を帯びて、市役所の香西さんという女性と「作戦上」結婚をして姓名を変えて住むことになる。その香西さんの所属していた「総務部となり町戦争係」だって急ごしらえの部署で心もとない一方、あとのほうになって、この戦争を起こすのに二十年も前から準備をしていた、とくる。おかしいではないか、お役所主導で20年前からやってきた事業ならば、その前準備として万全なる対策室が拵えられてしかるべきではないか、とまぁ、読めば読むほど作品のほつれが、ほつれじゃあないな、作品がほどけている部分が見えてくるのである。いわゆる現実とリンクした状態、つまり「考証」を旨とした場合は至極破天荒な作品といえる。
が、井上ひさしが本の帯で誉めてる。
<このすばらしさを伝えるのは百万言費やしても不可能>
ほー、すばらしさときたか、すばらしさと。
あれほど使われる日本語に注意深い井上ひさしが「すばらしい」って誉めてる。ここで筆者、ピンときた。ああそうか、これ、アレだわ。
『吉里吉里人』という作品を御存知だろうか。作者井上ひさし。北へ向かう特急列車がハイ(?)ジャックされる。ものすごい訛りの若者がこう宣言する「俺たちゃ、日本から独立して吉里吉里国になっただ、おめえら、入国管理局さ連れてくで」
(※ この辺、なんとなくの記憶で書いてる)
主人公の落ち目作家の男が、吉里吉里国で見聞きし、それから大統領になって殺されるまでの話、なのだけれども、結局、井上氏はこの『吉里吉里人』的なものを『となり町戦争』に見たのではなかろうかと考えるわけだ。二作品の共通点、それはいわゆる現実に対して躊躇することなく己の作ったパラレルワールドを提示できているところにある。五木寛之が選考評で<卓抜な批評性か、無意識の天才か。いずれにせよ桁はずれの白日夢だ>と書いているとおり、いわゆる我々の住む日本からシフトした日本を作り上げられているのには、作者の批評性というものが世界の外に向かって提示されている、ということなのだ。
もっとわかりやすくしてみよう。『吉里吉里人』『となり町戦争』どちらもその世界の外から見ると非常に歪んで見えるのだが、一度その内部に読者が入り込んでしまうと、今度は我々の住んでいた世界が歪んで見える、という仕掛けがあるのだ。小説は人間の普遍的な性や社会の風に根付いて書かれる、と申し述べたが、そういった現実の隣にいながら、作品自体はリアルから距離感をおいているのである。それゆえに、ある種ご都合主義的な展開があったとしても、一つの「作り話」だとわりきってしまえばいいのである。そのあたり「虚構」としての覚悟があるために、本作は創作として非常に冒険をし、大いなる収穫を得たものだと思う。
さて、主題。
リアル、これ、リアリティではなくて敢えてリアルなのだけれども、創作におけるリアルとはなんだろうか、という話である。今まで創作におけるテクネーとしての完成度の評価をしてきたけれども、五木の選評にもあるとおり、本作、まったく<白日夢>でしかないのである。時代の風、今の日本国の真実を創作の力によって暴く、大変その手腕は見事なものだ。だがしかし、そこにリアルを提示する以上の実感があるかというとイヤイヤサニアラズ。作者も初めのほうの志として広報に載せられる戦死者の数だけがリアル、なんて書き方をしていたが、結局は戦争という断片を出さないと話が進められなくなってしまっている。それでもなお虚構の枠を保てているのは、いわば偶然の産物といわれてもこれではいたし方ないのではないだろうか。
筆者、原因はわかっている。リアルではない戦争、という主題をもとに書き進めたものの、結局のところ小説を書くという作業が筋を追うという作業になってしまったものと見える。本作をお読みでない方のためにネタばらしは避けるが、北原と戦略的結婚をした町役場の香西さんの行く末、登場人物のむやみな関連付け、そういったもろもろを詰め込んで、結局「日本における実感のなさってこんなものなんじゃない?」と作者は嘯いている。
んだがね、ンなことは、わかってるのよ。
このあたりが問題なのだと考える。日本も戦後60年、敗戦の実感も薄れて、日本がアメリカと戦争をして負けたなんてことを知らないヤングどももいるんじゃないかしらん。そういった現状を踏まえて小説を書く。テレビの向こうに見える戦場の血なまぐささ。でも、その血なまぐささだってリアルじゃないんだよ、と。だけれども、我々はそんな日本に生きていることなんざ今更言われなくても理解ってる。小説書きだかなんだか知らないが、日本の髄を取ったような顔をして作品が提示されても、そういう現状に生きる我々はじゃあ実感としてどうするか、というのがリアリティなんじゃないだろうかね。女の子の気持ちは男の俺にはわからない。ああそうかい、で、おまえさんのみに何が起こったのさ? 百聞は一見に如かずじゃないけど、その事態において、作家自身はどう動いたか、なにが起きたか。真のリアリティーなんざ己の実感の中にしかないし、願わくば自分の肌で感じた風をその時代の風だと云って欲しい。般若心経でも云っているよ。色即是空、色(世界)は即ち空だ。世界は無常。そこで終わっちゃいかんのよ。空即是色、その空虚からすべては生まれる。ここまでこなくちゃ、この世界で生きるのは楽しくない。
まとめ:何を書いてもいいけど、いかに自分の実感にひきつけるか、というのがリアリティ。
今回の参考文献
三崎亜記『となり町戦争』(集英社)
井上ひさし『吉里吉里人』(ちくま文庫)
05/5/29/NAGASHIRO
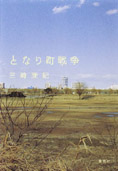 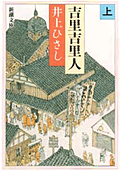
写真左より▲『となり町戦争』三崎亜記(集英社)『吉里吉里人』井上ひさし(ちくま文庫) |
|
| | |   
当Webサイトは FLASH PLAYER の最新バージョンを必要とします。 |
 |