筆者紹介
ながしろばんり
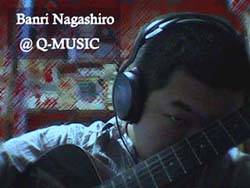
芸人。日本大学芸術学部文芸学科卒。著述から編集、イラストレーション、作詞作曲弾語りまで幅広くこなす大いなる器用貧乏として活動中。現在は編集者を経てフリー。亜空間創作ギルド万里園主宰、オンライン文芸集団・文藝越人六〇〇主宰。いくら仕事をしてもパッとしない仕事ぶりは「無冠の帝王」として語り継がれている。ハウツー本のライターからエロ小説まで、基本的に頼まれれば引き受けます。お仕事募集中。格安にて営業中。 寄稿リスト| 寄稿リスト|
第1回
第2回コモンセンス
第3回グロテスク
第4回剥製〜短編小説論 I
第5回空間〜空間小説論〜
第6回破綻〜ライトノベル論
第7回萌え〜判官贔屓のリアリティ〜
第8回リアル〜『となり町戦争』を読む〜
第9回お役所〜文字・活字文化振興法案(前編)
第10回施策〜文字・活字文化振興法案(後編)
第11回興味〜よいこのブックガイド
第12回センス〜ダビデ王とマシンガン
第13回春は化け物
 |
| | 森羅万象
 書く人のための文芸事情 書く人のための文芸事情
|
さて、どこから手をつけたもんやら、なのである。
書評といっても広うござんす。書評の対象となる文芸も広うござんす。かといって境界の設定からしていくのも退屈なわけで。色々考えた。リンゴを半分に切っても端っこから齧れるが、スイカを半分に切ってもきっかけがない。どうしたもんか。か、カラス。す、スリジャヤワルダナプラコッテ。て、手羽先、き、錦糸卵。ご、碁石……みんな食べ物だな。し……しりとり。
しりとり、である。しりとりのきっかけだってしりとりのりー! なんて云って始めるのだ。よし、決めた。前の回の文章の単語から繋げていくことにする。その位の企画力がなかったら面白くなさそうだし。じゃあまあ、続けられるところまで。よろしくおつきあいのほどを。
というわけでデュナミス。日常ではまったく聞かない言葉であろうし、わざわざタイトルにすえたのだから、始めに解説をしていく必要性があるだろう、ということだ。"δμναμιs"、日本語に置きかえると潜勢態、ないしは可能態。文字通りに考えてしまうと「勢いが潜ってる」これでいいのだ。難しく考える必要はない。
具体例をあげよう。日本人なので日本のことがいいだろうから、『古事記』より引いてみる。
むかーしむかし、まだ日本が高天原と黄泉に分かれていたころのお話。ある一人の神が、葦原の続くところに新たな国を作るべく励んでおった。これ、その後に国を作ったんで大国主だとか大黒様だとか呼ばれるのだが、当時の彼は色男でモテモテだったために色許男(しこを)なんて呼ばれている。葦原のシコヲさん、別名八千矛神なんて呼ばれるけれども、これも八千本の矛。もう、激しくズボズボ差すのである。のっけからこんなんで申し訳ない。
シコヲさんはスセリ姫なんていう嫁さんを貰って昼には大地に種を撒き、夜には嫁などに種を撒く。なにしろエネルギーの塊で精力絶倫、ついには大土持(オオナムチ)なんて崇められますが、やはり日本いっこ作るのは大変。怪力でならしたシコヲにもほとほと疲れ果てる。
と、そこに波の向こうからなんだかちっこいのがやってくる。ががいもの実で出来た船に乗って、蛾の革を剥いで着こんでいる。名前を聞いても答えない。お伴の者に聞いても誰も知らない。近所のガマガエルが「カカシノクエヒコなら知っているでしょう」という。カカシノクエヒコ、名前の通り歩くことはできないが天下のことはなんでも知っている、という神様。クエヒコに聞いてみる。「彼はカムスヒノカミの御子、スクナヒコナです」ははぁ、じゃあシコオと兄弟じゃないの。シコオも母親のカムスヒノカミに聞いてみる。認知されました、兄弟力を合わせて国を作れという。
さて、兄弟を合わせるとすごいすごい。一挙に国を作り上げてしまった。国をつくりあげると、スクナヒコナ、またふい、と海の向こうへと帰ってしまう。
……と、そういう話だ。察しのいい読者諸氏なら色々な疑問が浮かぶことだろう。桃太郎ではないが、なんで桃から生まれたのだ、なぜお供が人間ではなく犬猿雉なのか。そういったことと同様の疑問である。黙って寝なさいではすまないのが当コラムなのであるからして、ちょっと挙げてみる。
・スクナヒコナのような小さい助っ人が、一体何をしたのか。(なにしろ、蛾の革を剥いだ着物である)
・誰も聞いたことの見たこともない「神」とはどういうことか。
・スクナヒコナは、何故一言も喋らないのか。
・スクナヒコナ、なんで帰っちゃったのか。
カカシノクエヒコというのは非常にわかりやすい存在である。つまり、彼が居ないと話が進まないといった手合いの存在である。話の都合上解説役が出てくるとは何ともわかりやすい話だが、とにかく、このスクナヒコナって何だ、という話になってくる。誰も知らない。あちらからの言葉はない。しかし、怪力無比のシコヲを助け、とうとうは日本こと中つ国を造ってしまった。そして、ふいといなくなる。他の文献に当たってみますってぇと、この中つ国から海を渡ったところにあるのは常世の国であるという。スクナヒコナは常世の国からやってきて、常世の国に帰っていったのだ。
と、ここまできて詰まったのでデュナミス本体に戻る。
デュナミスという単語自体はアリストテレスである。アリストテレスがいうところの二位一体説、というところが一つのポイントで、表立ったエネルギーであるところのエネルゲイア(ενεργεια)、そして潜っている勢力であるデュナミスがあるという。つまりこれは人間の持つ力のシステムとして、この二つが介在している、という理論だ。身近なところでは火事場の馬鹿力、なんてのも入るかもしれない。潜っているから普段の、本人は気づかない。本人にはどうしようもない、もろもろの力。
ここまでくれば、ピンと来た方もいるのではないかしら。
古事記でのオオナムチ−スクナヒコナの関係性というのは、この二位一体の関係性なのである。誰も知らない神、誰も聞いたことのない神、そりゃあ当然だ。潜勢態として、スクナヒコナは常に知の背後に存在する。人間、モノを認識するときには、つねに知の前にあるからこそ認識できるのである。つまり、スクナヒコナとは、スクナヒコナのいる「常世」とはオオナムチの中にあった、ということになる。いわゆる、知の背後の存在である。この知の背後に存在するものが、何かの拍子で知の前に投げ出されたとき、我々はそれを認識できるのだ、と言える。つまり、物言わぬスクナヒコナは、私(=生)の中にありながら、絶対的な他者なのである。
十九世紀から二十世紀にかけてフロイトなんていうおじさんがおりましたが、彼の言う自我−超自我なんていうのも、結局はこの二位一体説の延長上にあるといえる。逆に心理学から逆算すると、古事記の例は明瞭になるに違いない。オオナムチが人間のエゴの神格化なら、スクナヒコナはスーパーエゴ、つまりは超自我の神格化ということになる。
人間の内部にありながら、人間が掌握できない世界。夢、性的衝動、感情、本能、そして「知」そのもの。知の背後にあるものがすとん、と目の前に投げ出されたとき、人はそれを霊感だのインスピレーションだのと呼ぶ。中つ国こと日本を創造するという作業において、オオナムチこと人間Aは知の前提にある知が認識の前に投げ出されたことによって、通常では有り得ない理力を発揮したのだ、ということである。
さて、筆者は以上のシステムにしたがって、文芸を、ひいては芸術を定義することにする。つまり、芸術において為す仕事というのは、知の前提にある存在をそれぞれの手法を持って実在に持ちかえる作業である、と考える。それは理想論だとしても、せめて、実際には五感で捉えられないものを、五感に置きかえるということが芸術の使命であると考えるのだ。本コラムは書評についてのことであるからもっと範囲を狭めると、文芸で為すことは何か? という問への答えは「人間の感情」ないしは「存在しない世界の構築」ということにでもなるだろうか。
QBOOKSの投稿作品でも、例えばネタだとか特異な設定だとか、そういったものだけを書いてそれで満足している作者が往々にしているわけなのだけれども、ネタや設定やもろもろの話の筋というのは所詮、小説のための小道具でしかないのである。インターネット界においてもブログをはじめとした個人の日記が非常に流行しているのであるが、あれだって結局は筆者である人間の感情や人間性が面白いのであって、最近あった中越地方地震を取り上げるのでも、人によって取り上げ方や視点が違うから面白く読めるのですな。そう、実は話の中身なんかなんでもいい。いかに演じたり体験したりしている人間の視線や人間性が書けているか、なのである。水戸黄門だって遠野英二郎と里見浩太郎じゃぜんぜん別物なのであるし。
といったところで字数が尽きた様子。面白かった方はまた次回のお楽しみ。そうでないかたは、お退屈様。
参考文献
・『古事記』(七)少名毘古那神と御諸山の神
・日本大学の相川宏教授(芸術学)の理論をずいぶんと参照しました。04/10/25/NAGASHIRO
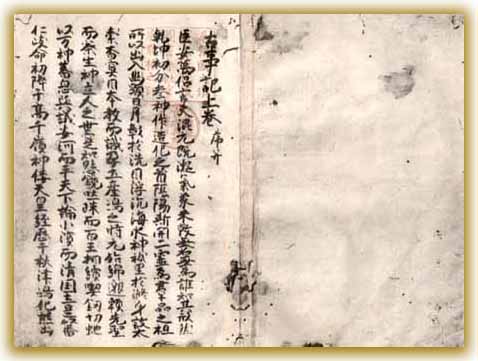
写真▲『古事記』上巻原文。
|
|
| |   
当Webサイトは FLASH PLAYER の最新バージョンを必要とします。 |
 |